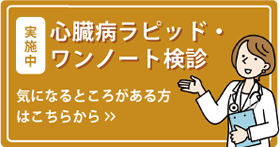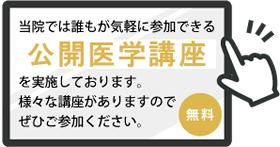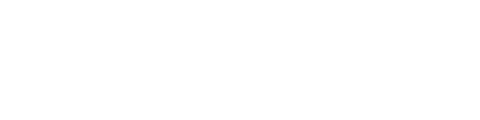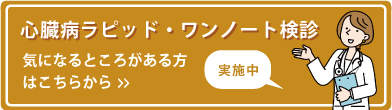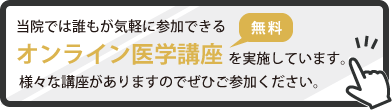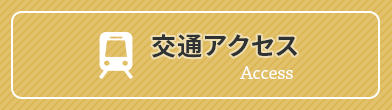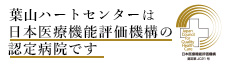お電話でのお問い合わせ
046-875-1717
健診センター問い合わせ専用ダイヤル
046-875-3533 (月~金 13:00~16:00)
046-875-3533 (月~金 13:00~16:00)
文字サイズ
- 中
- 大
Googleカスタム検索